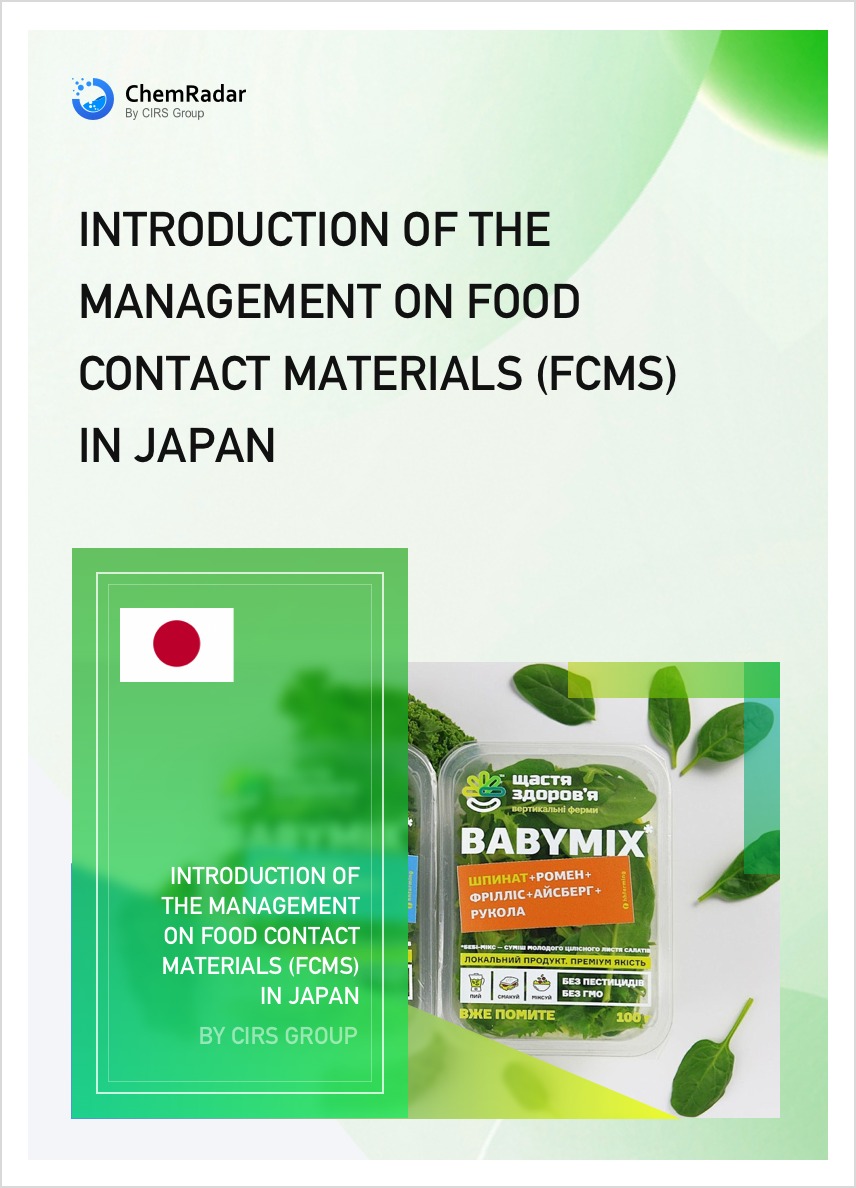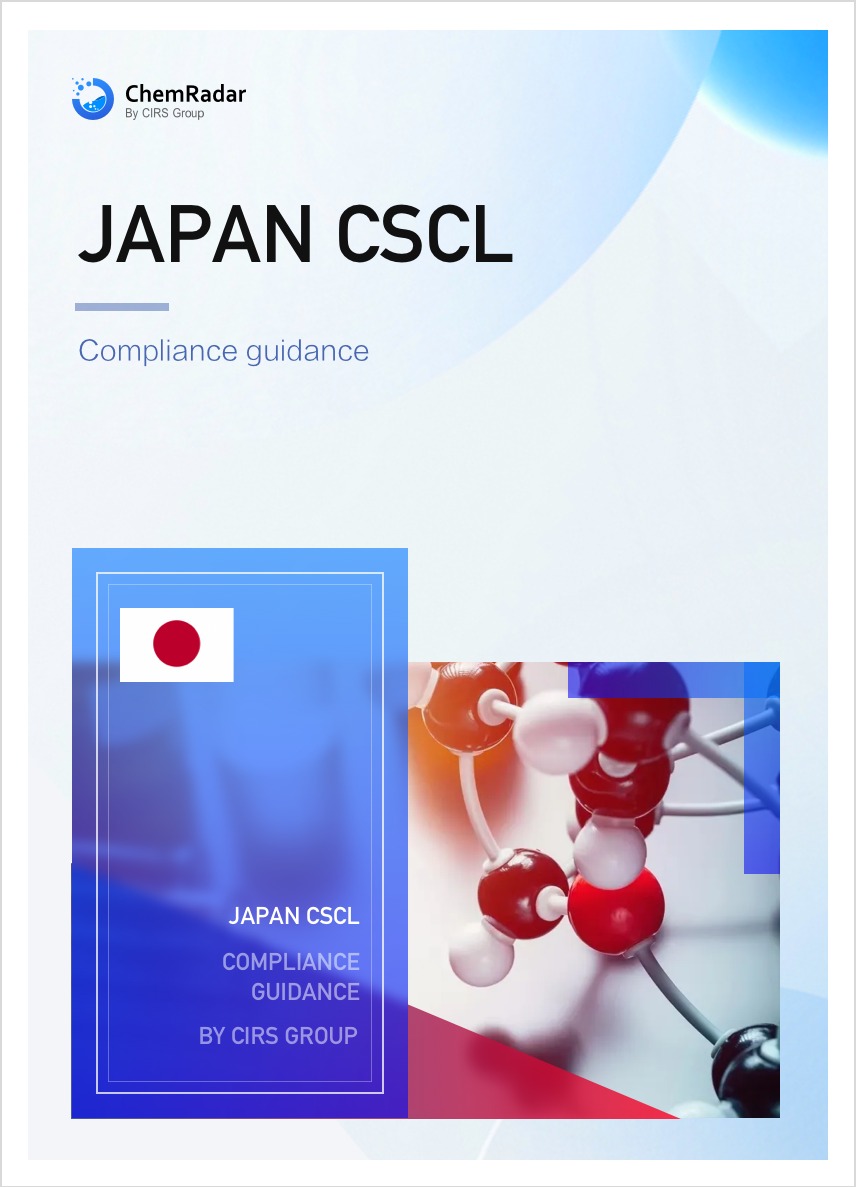最近、日本の’厚生労働省(MHLW)、経済産業省(METI)、環境省(MOE)が共同で、国立研究開発法人産業技術総合研究所(NITE)のウェブサイトに2024年度GHS推奨分類リストを公開しました。 このリストは化学リスク管理を行う企業にとって重要な参考資料を提供します。
この更新では、化学物質管理法(CSCL)および労働安全衛生法(ISHA)に基づき、186物質の分類情報を改訂しました。そのうち43物質は新規分類され、143物質は既存の分類が改訂されています。リストには物質名、CAS番号、物理化学的危険性、健康危険性、環境危険性の3つの危険区分にわたる評価結果が詳細に記載されています。日本は化学物質の流通および使用時の人の健康と環境保護を強化するため、化学ラベルおよび安全データシート(SDS)作成の統一的指針を提供し、年次更新の仕組みを実施しています。
企業責任による自主的適用
- 任意の参考:日本政府はこのリストの分類結果があくまで自主的な参考用であることを明確に強調しています。企業はGHSラベルやSDS作成時にリスト内容を自由に引用またはコピーできますが、法的義務ではありません。
- 企業の意思決定の自主性:企業は保有する他の科学的データや試験結果に基づき、推奨リストと異なる分類結果をラベルやSDSに採用する権利を有します。
- 最終的な責任:推奨リストを採用するか否かにかかわらず、企業は自社のラベルおよびSDS情報の正確性と適合性について責任を負わなければなりません。
GHS標準分類と推奨分類
- GHS標準分類:これは国連の化学品の分類および表示に関する世界調和システムの中核的枠組みであり、日本で法的効力を持ちます。化学物質の危険性を識別・分類する基準と、ラベルおよびSDSの統一フォーマットと内容を規定しています。国際的に義務付けられた規則です。
- 日本の’推奨分類:このリストは日本政府が国内の化学安全管理の特定ニーズに対応するために作成した地域化された実施指針です。GHS国際基準に準拠しつつ、日本の市場実態(例:日本国内でのみ製造または使用される化学物質に特別規定がある場合など)に柔軟に対応するため、より詳細かつ的確な分類推奨や情報を提供することが多いです。法的拘束力はありませんが、実務上非常に価値のある参考資料となっています。
日本の化学安全管理システムは、GHS標準分類と推奨分類の並行運用を通じて、国際規範との整合性を保ちつつ国内の産業および規制ニーズに対応しています。このアプローチは規制の柔軟性と実用性を提供し、企業の情報適用における主たる責任を明確にしています。企業は両システムの違いと関連性を十分に理解し、適合を確保する必要があります。
詳細情報